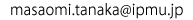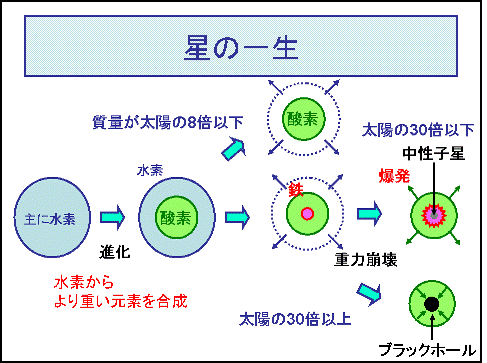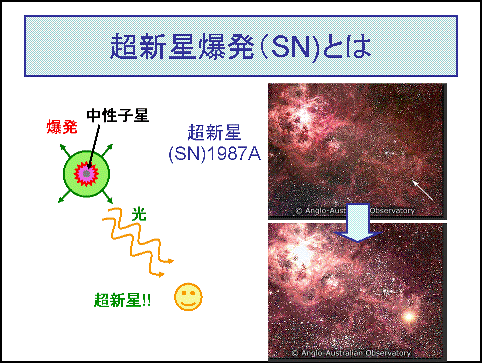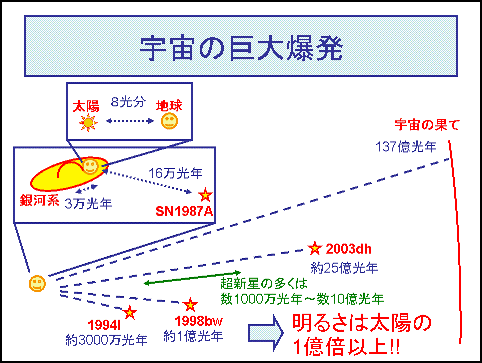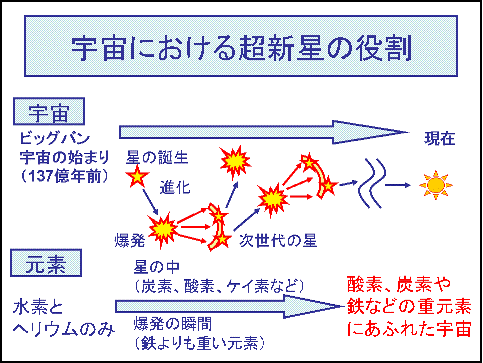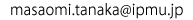星の一生の最期に新たな形態が存在
ー中性子星の誕生が引き起こすガンマ線バーストと超新星の発見ー
1. 星の進化と超新星爆発
星の進化
自ら光を放って輝く恒星は、非常に長い年月をかけて進化します。
その質量が太陽の質量の8倍より小さい星は、
進化の末外層をなくし、白色矮星としてその生涯を静かに終えます。
一方で、質量が8倍よりも重い星は中心にできた鉄のコアが重力崩壊を起こし、
超新星爆発として華々しくその生涯を終えると考えられています。
しかし、太陽よりも30倍以上重い星はその重さ故に、重力崩壊の際に
ブラックホールを作ってつぶれてしまい、超新星にはならないと考えられていました
(その後の展開についてはこちらをこちらを参照)。
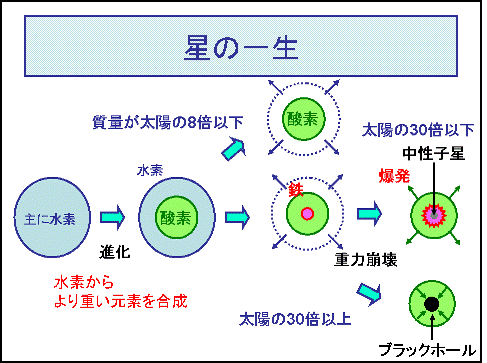
超新星爆発
中性子星を残して爆発を起こした恒星は、超新星、すなわち空にある星が突如
急激に明るくなる現象として観測されます。
SN 1987Aは隣の銀河、大マゼラン雲で起こった超新星で、
この超新星からのニュートリノがカミオカンデで検出されたことで
一躍有名となりました。
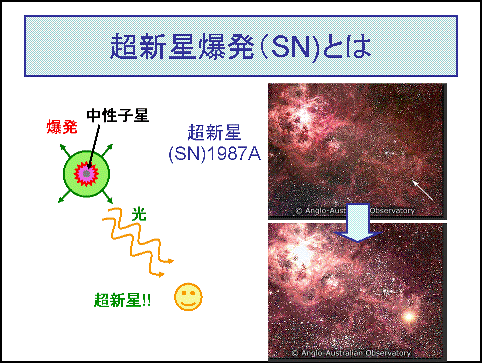
h2>超新星までの距離
SN 1987Aは我々がこの1000年間で経験した最も近い超新星で、
我々の銀河系では1056年以来超新星が観測されたことはありません。
現在、超新星が観測される平均的な距離は数億光年です。
そのような非常に遠方で起こっても観測できることから分かるように、
超新星爆発は星一つの爆発であるにも関わらず大変明るく、
その明るさは星が100億個程度集まってできた銀河と同程度にもなります。
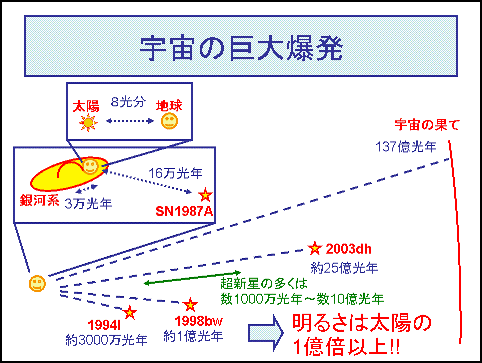
宇宙における超新星の役割
超新星は爆発時に大量の重元素を合成します。
また星の進化の課程で作られた元素も爆発時に
まき散らされ、超新星爆発によって宇宙は重元素をふやしていく、と考えられることができます。
宇宙がビックバン始まったときには、水素、ヘリウムとごく微量のリチウムしかなかったと
考えられており、超新星爆発は我々の太陽や地球を構成する元素を宇宙に
供給しているという意味で、非常に重要な役割を担っています。
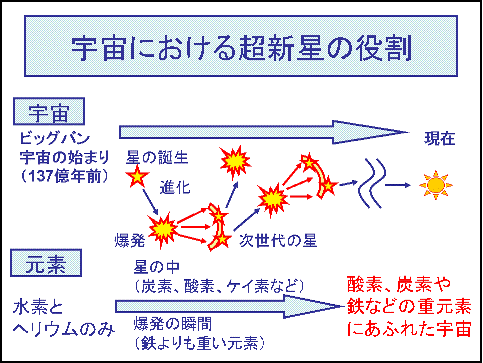
用語解説
- 白色矮星:
太陽の8倍よりも軽い星の最終形態。水素を燃やして中心で
ヘリウム、炭素、酸素、を順に合成していき、
最終的に炭素と酸素でできた中心部だけが残った状態のことを指します。
それより外側の水素を中心とする層は恒星風として飛ばされ、惑星城星雲として観測されます。
- 光年:
光の速度(秒速30万km)でその時間に進む距離。
太陽からの光は約8分かけて地球に届くので、太陽までの距離は8光分と言うことができます。
1億光年の距離で起こった超新星と言ったとき、地球に届いた光は、
実際は1億年前に起こった爆発からの光ということになります。
- 重元素:
天文学では水素とヘリウム以外の元素を総称して重元素、と呼ぶことが多い。
鉄とそれよりも軽い元素は星の進化の課程でも作られるが、超新星爆発時には
鉄よりも重い元素も合成される。
Masaomi Tanaka
Department of Astronomy, Graduate School of Science,
University of Tokyo