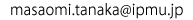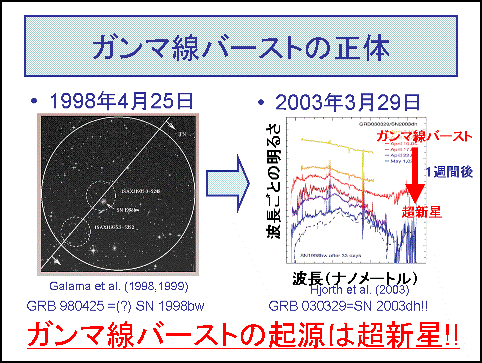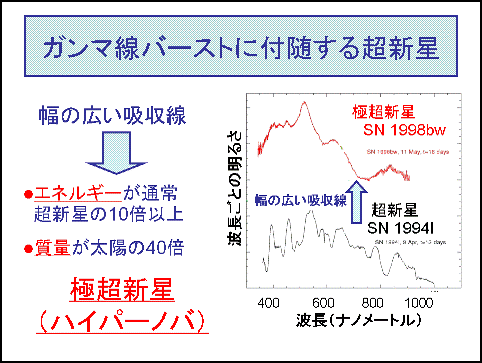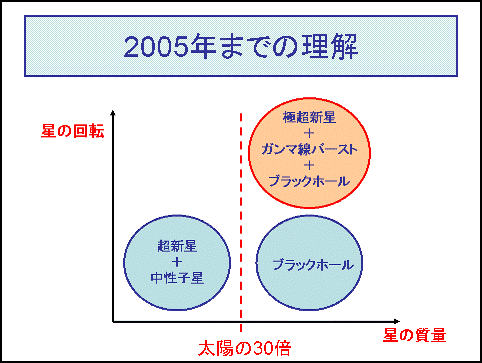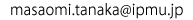星の一生の最期に新たな形態が存在
ー中性子星の誕生が引き起こすガンマ線バーストと超新星の発見ー
2. ガンマ線バーストと超新星
ガンマ線バーストとは
ガンマ線バーストとは宇宙のあらゆる方向からやってくる、突然のガンマ線放射現象で、
1960年代の発見から30年近くその正体は全くと言ってよいほど不明でした。
1997年にガンマ線バーストの残光が可視光で発見されて以来、
それぞれのバーストまでの距離が決定され始め、そのほとんどは数10億光年という非常に遠方で
起こっていることが分かりました。
距離が分かったことで、その全放射エネルギーが明らかになりました。
その結果、典型的には(等方に放射していると仮定した場合)10の53乗エルグ
という途方もないエネルギー
が放射されていることも分かりました。
ガンマ線バーストと超新星
ガンマ線バーストに対する理解が一気に深まったのは1998年のことでした。
BeppoSAX衛星が検出したガンマ線バーストと同じ位置で超新星が発見されたのです。
さらに2003年、ガンマ線バーストの残光のスペクトルを
可視光観測し続けた結果、それが明らかに超新星のスペクトルに変化したことが確認されました。
これらの結果から、研究者たちは、ガンマ線バーストの起源は超新星である、
すなわち質量の大きい星の最期の姿であるという確信を持ったのです。
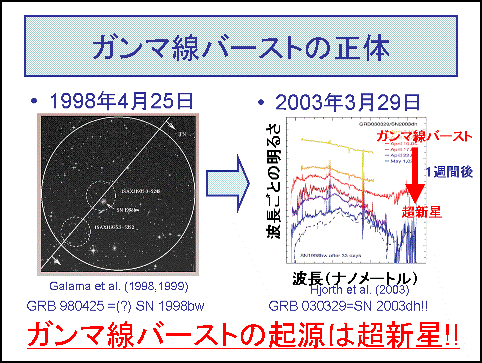
極超新星
ガンマ線バーストに付随して発見された超新星は2005年までに
3例あり、そのどれもがスペクトルに幅の広い元素の吸収線を持っていました。
吸収線の幅の広さは、爆発して膨張する物質の速度を反映しており
(ドップラー効果)、
その解析から爆発のエネルギーは通常の超新星よりも10倍ほど大きいことが分かりました。
このようにエネルギーの大きい超新星を極超新星と呼びます。
また、明るさの変化の解析と合わせて、このような超新星は太陽の40倍以上の質量をもっている
ことも分かりました。
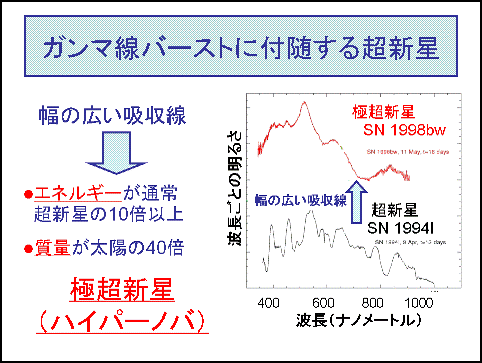
大質量星の最期
極超新星の発見により、太陽の40倍以上の質量を持つ星も最期には爆発することが分かりました。
このような場合は、通常の超新星よりもエネルギーが10倍ほど大きく、
その爆発メカニズムはブラックホールが深く関係していると考えられますが、
まだ完全には理解されていません。
星の自転速度の違いによってブラックホールに全てが飲みこまれ爆発しない場合と、
非常に激しく爆発する場合に分かれるのかもしれません。
s
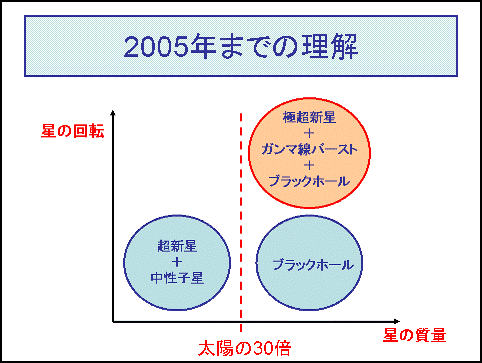
用語解説
- ガンマ線バースト:
高いエネルギーの電磁波であるガンマ線が約0.01秒から数
100秒間にわたって観測される現象。継続時間が2秒以上のものはロングガンマ線バー
スト、2秒以下のものはショートガンマ線バーストと呼ばれています。今回のバース
トはロングガンマ線バーストに分類されるものであったため、ここでは単にガンマ線
バーストと呼んだときロングガンマ線バーストを指すものとします。
- スペクトル:
光を波長ごとに分解して、それぞれの波長の光の強度を比べたもの。
ガンマ線バーストのスペクトルは起伏がないのに対して、
超新星のスペクトルは様々な元素による吸収により、よりでこぼこした形になります。
- ドップラー効果:
近付いてくるものから発せられる音が高くなる(波長が短くなる)のと同様に、
音と同様の波である光も、近付いてくるものは波長が短く(より青く)なります。
元素の吸収線の位置はその元素によって決まっていますが、超新星自体が
秒速数千から数万kmで膨張しているため、その物質が吸収する光も
より青くなります。この光のずれ方を観測することで、逆に速度を求めることができるのです。
Masaomi Tanaka
Department of Astronomy, Graduate School of Science,
University of Tokyo