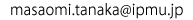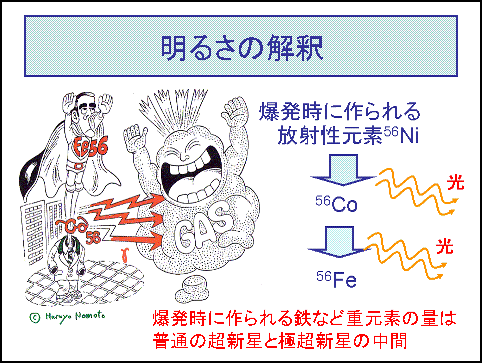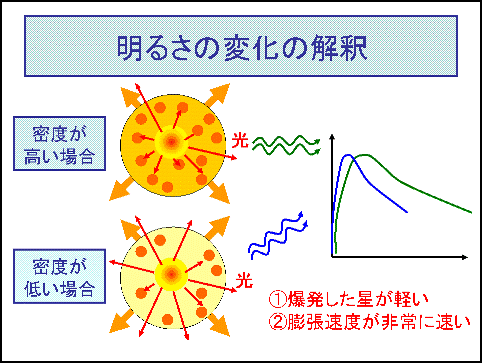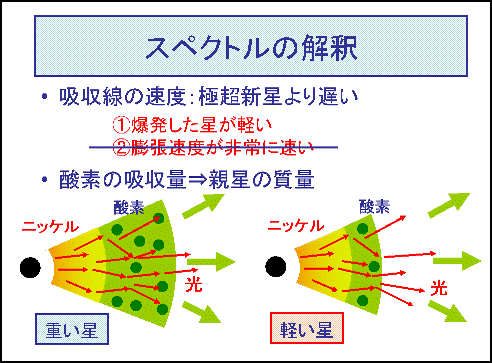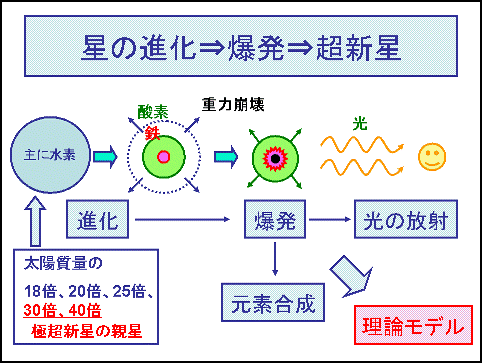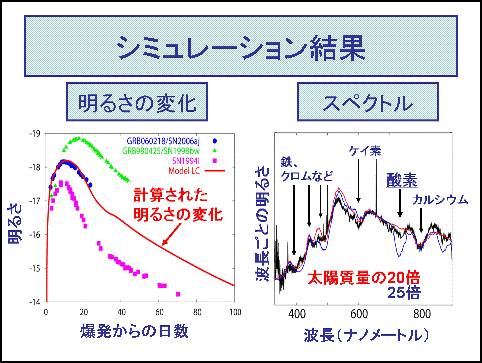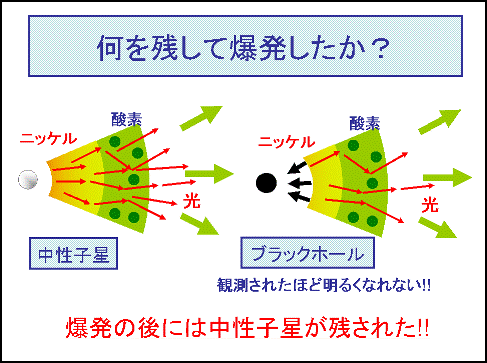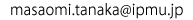星の一生の最期に新たな形態が存在
ー中性子星の誕生が引き起こすガンマ線バーストと超新星の発見ー
4. 超新星観測結果の解釈
明るさの解釈
超新星の爆発の瞬間には放射性元素の56Niが合成されます。
この元素がまず56Coに、続いて56Feに崩壊するときに放射されるガンマ線により、
超新星物質があたためられ、超新星は光ることができます。
すなわち、一番明るくなったときの明るさは爆発時にできた56Niの総量を
表しており、今回の超新星ではその量が普通の超新星より多く、極超新星より少なかったと言えます。
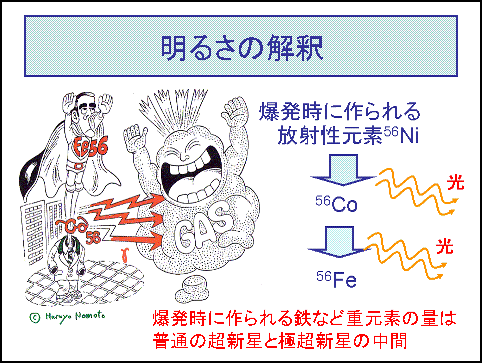
明るさの変化の解釈
明るさの変化の仕方は、膨張する超新星物質の濃さを反映しています。
56Niは爆発の最も内側で合成されるため、そこから出てきた光は超新星物質を
通り抜けるのに時間がかかります。
非常に濃い超新星物質があるとなかなか光は出てこないため、光度曲線の
変化の仕方(例えば明るくなる早さ)は遅くなります。
今回の超新星が極超新星よりも早く明るくなったという事実は、
典型的な極超新星よりも超新星物質が薄くなっていることを示唆しており、
-
超新星の親星の質量が軽いために薄い
-
膨張速度が極超新星よりも速いために、極超新星と同じ質量でも薄い
という二つの可能性が考えられます。
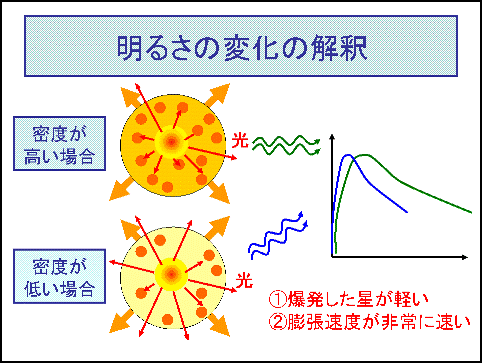
スペクトルの解釈
スペクトルに見られる吸収線の速度は極超新星のものよりも遅かったので、
上述した、膨張速度が速いために超新星が薄くなっている、という可能性は
棄却されます。
また酸素の吸収量が少ないということは、そのまま酸素含有量を反映しているので、
れもまた、親星が軽かったことを示唆しています。
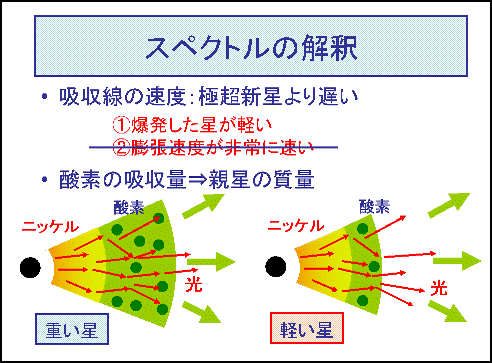
シミュレーション結果
今まで行ってきた議論は全て親星が軽いことを示唆していますが、ではどの程度の質
量か、という問いに答えるためには、理論的な計算を行う必要があります。
我々はこの可能性を検証するために、星の進化をシミュレーションで追い、
その星を爆発させ、どのような元素がどれほど合成されるか、どのように光るか、
という一貫したシミュレーションを行いました。
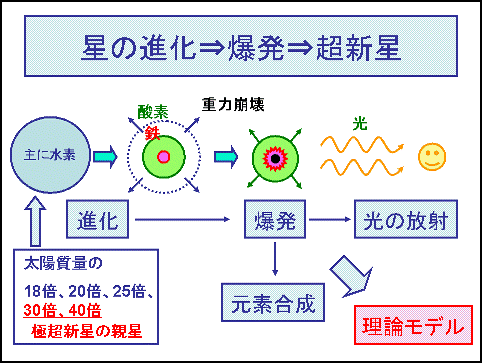
その結果、太陽の18倍の星では十分な吸収線の速度が得られず、25倍以上の星では
観測されるスペクトルに酸素の吸収線が強くなりすぎることが分かりました。
よって我々は、今回起こった超新星は親星の質量が太陽の20倍程度であったと結論しました。
爆発エネルギーは通常の超新星の2倍でこれは普通の超新星と極超新星の中間です。
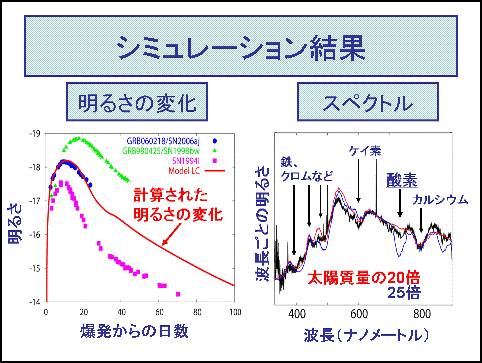
中心に残された天体
太陽の20倍の質量の星は、中性子星を残して、普通の超新星になると考えられてきました。
今回も20倍という値が得られているので、中性子星が中心に残されたことが予想できます。
ではそもそもこの定説はあっているのでしょうか?ガンマ線バーストが出ているということはやはり
なんらかの知られていない理由でブラックホールが作られたのでしょうか?
中心に残された天体を観測的に探るのは容易ではありません。
もちろん距離が遠すぎてパルサーを確認できることもないですし、
中心天体は光を放つ訳ではないので、可視光の光度曲線、スペクトルにも
そのシグナルは全くないのです。
しかし、私達による元素合成の計算(56Niができる領域と量の計算)によれば、中心天体
は中性子星だと考えられます。中心にブラックホールほどの重い天体が残ってしまう
と、せっかく作られた56Niの大部分がブラックホールに飲み込まれてしまいます。
その結果、この場合には観測値を説明できるほどの量が放出されないことが分かりました。
すなわち、やはり中心には中性子星が残っていないとこの超新星の観測的特徴は
説明が不可能なのです。
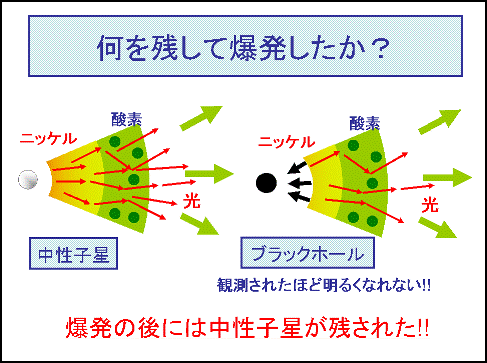
Masaomi Tanaka
Department of Astronomy, Graduate School of Science,
University of Tokyo