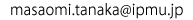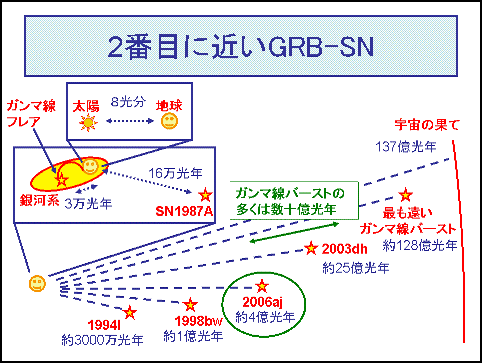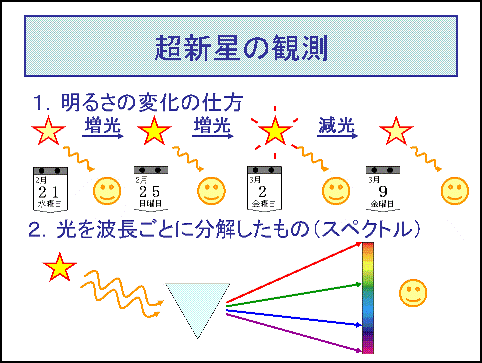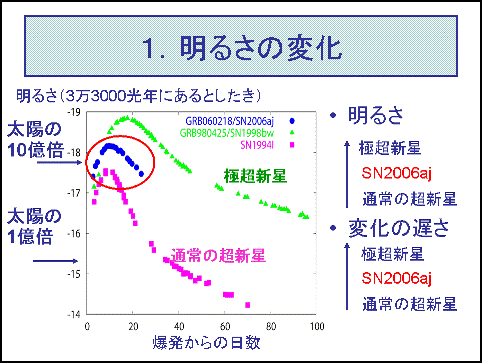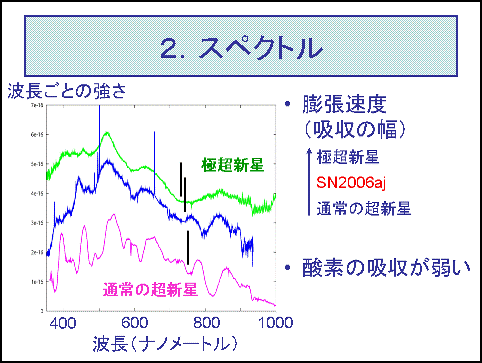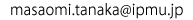星の一生の最期に新たな形態が存在
ー中性子星の誕生が引き起こすガンマ線バーストと超新星の発見ー
3. 今回のガンマ線バーストとそれに付随した超新星
GRB060218と付随する超新星の発見
2006年2月18日、牡羊座の方角、4億4000万光年先で起こったガンマ線バーストを
NASAのSwift衛星がとらえました。
このガンマ線バーストはSwift衛星が運用されてから最も近いところで起こった
バーストであったため、世界中の研究者は超新星が現れることを期待して
地上の可視光望遠鏡をその方向に向けました。
我々も日本の所有するハワイのすばる望遠鏡を使って観測を行おうと計画しましたが、
悪天候のため断念せざるを得ず、国際協力によりチリのVery Large telescope (VLT)
を使って観測を行うことになりました。
そして、観測の結果、超新星SN 2006ajを可視光で発見することができたのです。
今回のガンマ線バーストは、主にエネルギーの低いX線を放射する現象で、
厳密にはX線フラッシュと呼ばれています。
このカテゴリーに分類されるバーストから超新星が現れた証拠が
これほど明らかに得られたのは初めてで、
今回の発見により、X線フラッシュも超新星を起源としていることが決定的となりました。

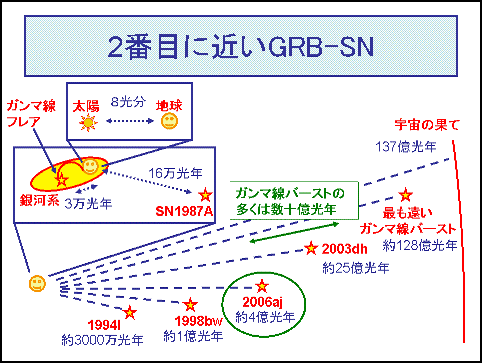
VLTによる観測
どのような星が超新星を引き起こしたかを探るためには、少なくとも
明るさの変化(光度曲線)、光を波長ごとに分解したもの(スペクトル)を
観測し、解析する必要があります。
我々は光度曲線をほぼ1日おきに取得し、スペクトルの時間発展まで
正確に観測することで、解析の精度を高めることができました。
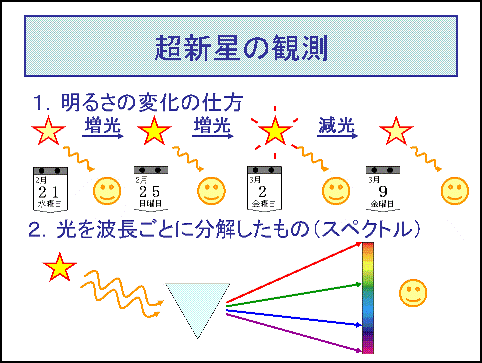
光度曲線
SN 2006ajの明るさと変化の早さはどちらも普通の超新星と極超新星の中間でした。
残念ながら、
地球の公転の影響により爆発後30日程度で太陽の影に隠れてしまったため、
観測を続けることができませんでした。
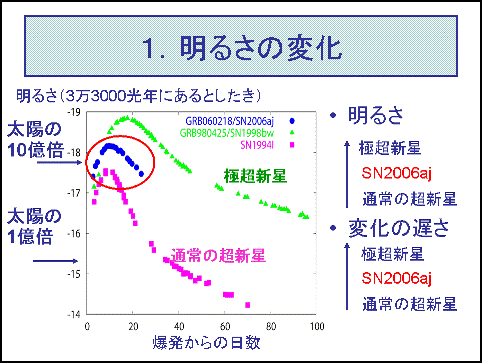
スペクトル
ドップラーシフトから測った膨張速度は通常の超新星と極超新星の中間でした。
また、750ナノメートル付近にみられる酸素の吸収線の強度がこれまでの超新星よりも
非常に弱いことが特徴的です。
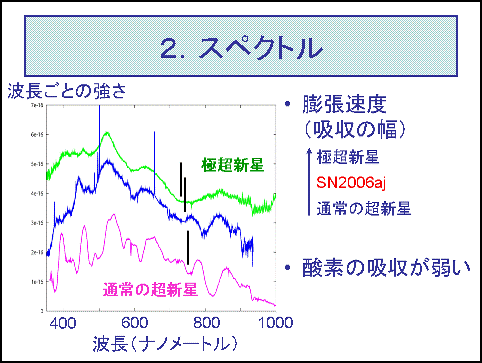
Masaomi Tanaka
Department of Astronomy, Graduate School of Science,
University of Tokyo